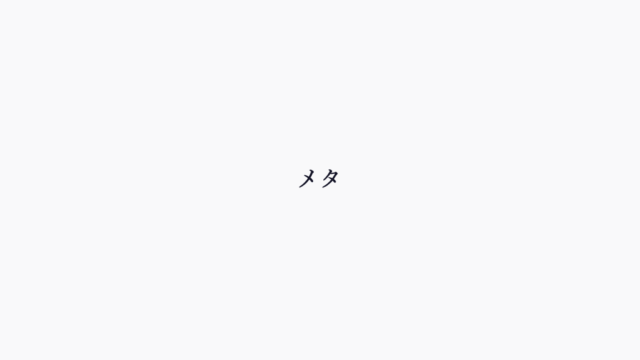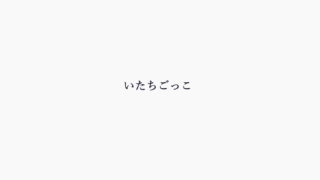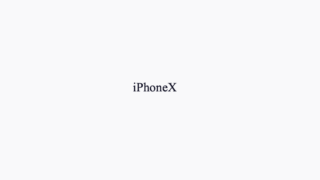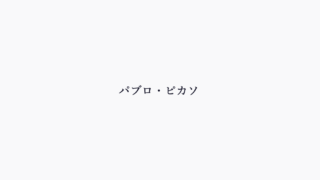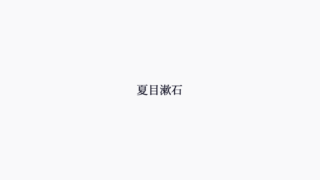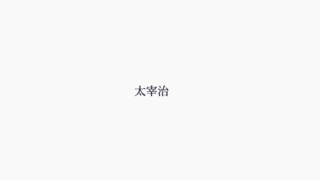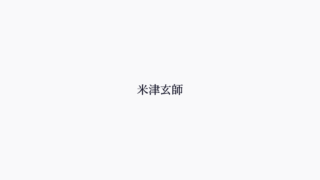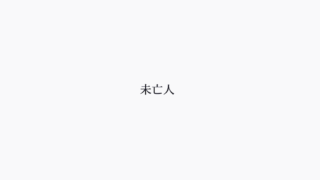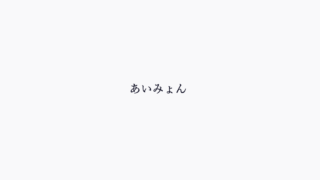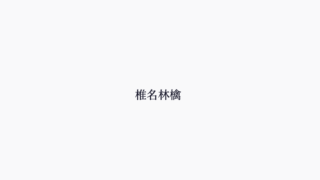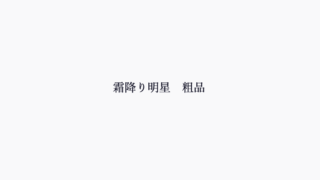無印良品の名前の由来
無印良品の歴史
無印良品と言えば、アパレルから生活雑貨、食材まで様々な商品を提供する日本を代表するブランドで、私服を選んだり日々の暮らしや引越しで生活用品を揃えるときにも便利な生活に根ざした企業です。
また、無印良品は日本だけでなく海外でもMUJIとして世界中で受け入れられています。
それでは、無印良品は一体いつ頃から始まったのでしょうか。以下、ざっくりと無印良品誕生の歴史を紐解いていきたいと思います。
まず、無印良品は1980年、「わけあって、安い」をキャッチフレーズに良品計画の母体である西友の自社ブランド商品としてスタートします。最初の商品は、「われ椎茸」と「鮭の缶詰」でした。
干した椎茸は、生のものに比べて旨みや香りが強く、栄養価も高く、戻し汁は風味豊かなダシにもなります。味にも栄養にもすぐれ、家庭料理の基本ともなる食材なのに、日常使いする人が減っている。その理由のひとつに、「値段」があるかもしれません。「干し椎茸は高い」というのが常識。その常識をくつがえしたのが、無印良品の「こうしん われ椎茸」でした。
安さの秘密は、カタチや見映えにとらわれず、不揃いのものや割れたものも一緒に販売したこと。大きさを揃えたり割れたものをはじいたりする選別工程を省き、割れたものも活かすことで、100g 568円という低価格を実現したのです。
デザインだけでなく、素材や生産工程もシンプルに簡素化。ただ安いというだけでなく「美意識を持った安さ」を魅力とし、徐々に社会に浸透、1983年には無印良品の第一号店が青山にオープンします。
その後、1989年には良品計画という社名で独立。「無印良品」というブランド名はそのまま継続し、紆余曲折を経ながらも、無印としての基盤の哲学は守りながら着実に広がり、今日に至ります。
ブランド名の由来
この「無印良品」という少し変わったブランド名ですが、名前の由来は無印の企業理念と密接に関わっています。
無印とは、文字通り、印が無いこと。強いブランド(印)で勝負するのではなく、素材や質の特性を前面に出していくという理念が、その名の由来です。
数多くのブランドが乱立し、素材や質よりもブランドという名称に値段がついているような時代、また「あれがいい」という欲望ひしめくなかで環境破壊が進んでいったことに対する問題意識などが、この「無印」という名前の根っこにあります。
無印良品は企業として2003年に次のようなメッセージを発信しています。
利益の独占や個別文化の価値観を優先させるのではなく、世界を見わたして利己を抑制する理性がこれからの世界には必要になります。そういう価値観が世界を動かしていかない限り世界はたちゆかなくなるでしょう。おそらくは現代を生きるあらゆる人々の心の中で、そういうものへの配慮とつつしみがすでに働きはじめているはずです。
1980年に誕生した無印良品は、当初よりこうした意識と向き合ってきました。その姿勢は未来に向けて変わることはありません。
これはメッセージの一部ですが、「無印良品の未来」全文を読むと、なぜブランド名を無印良品にしたのか、その由来となった企業理念がいっそう深く伝わってきます。
ことさらにブランド名の価値だけで値段が上昇していくのではなく、たとえば買い物をする際に、「無印でいい」と思えるような、そして、その「で」の品質をあげることで美的な理性が育まれることに貢献する、というのが無印良品の哲学にはあります。
この「無印」であることが海外のひとにとっては日本文化の「禅」とも結びつき、禅の精神を体現する生活ブランドとして、さらにファンを惹きつける要因になっているようです。
MUJIが海外で語られる際には、日本文化や日本古来の美意識と結びつけられることが多い。良品計画の松﨑曉社長は、「無印良品の商品は、無駄を省いた日本的な『わびさび』なものと消費者に受け止められ、特徴を出せている」と述べている(日本経済新聞、2016年3月20日)。「わびさび」は、茶道によって発展した考え方である。
禅や茶の本を読み解いていくと、MUJIと似通った概念が読み取れる。これは、MUJIの誕生、コンセプトづくりに大きく関わった田中一光氏が、茶道にも通じていたからであろう。