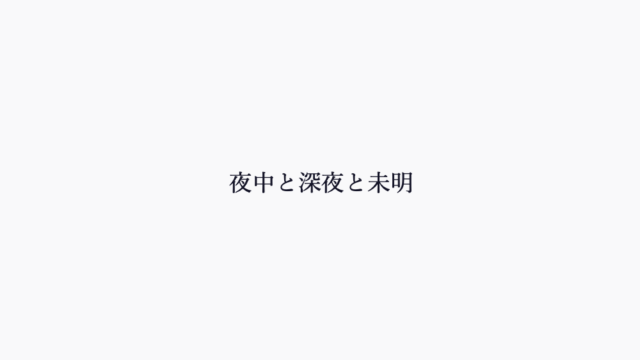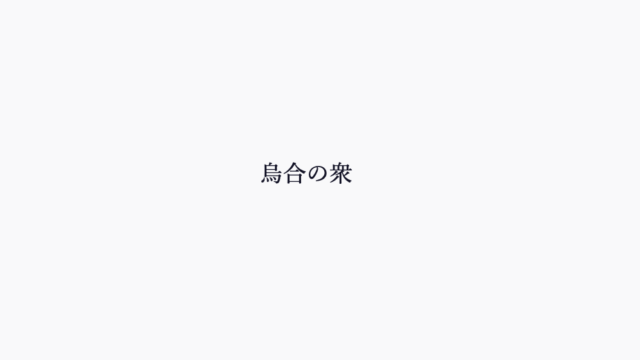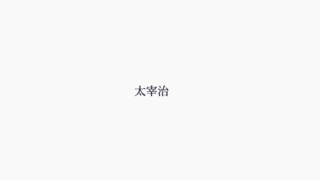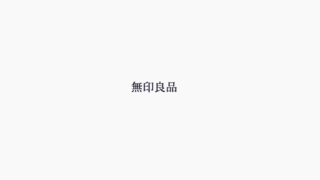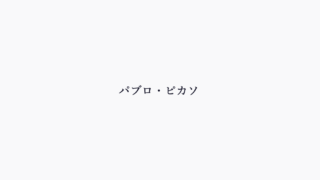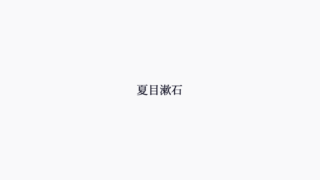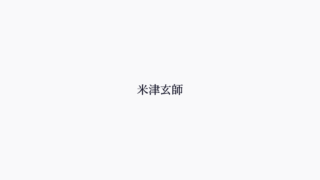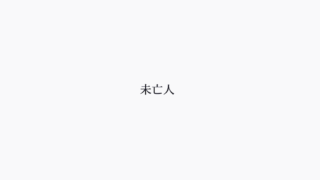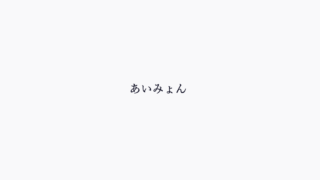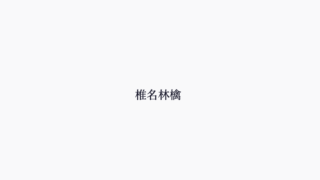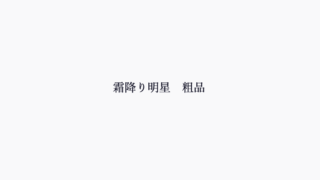いたちごっこの語源、由来、英語訳
日本語の有名な慣用句に、「いたちごっこ」という言葉があります。意味は、「両者が同じことを繰り返し、らちがあかないこと」を指します。
それじゃ結局はいたちごっこだよ、といった風に普段も割と使う言葉なのではないでしょうか。
文学作品のなかでも登場する言葉で、たとえば、以下のような例文があります。
例文
この世界は、仕組みを完全に理解するには少々複雑過ぎる。 追いついたと思うと、その先端はもっと前に進んでいってしまい、いたちごっこはいつまでたっても終わりそうにない。
出典 : 鈴木光司『ループ』
農薬への耐性をそなえ、高濃度あるいは新しい薬でないとびくともしなくなっている。 このいたちごっこはずっとつづいているのだ。
出典 : 星新一『きまぐれ博物誌』
出典 : 井上ひさし『コメの話』
他にも、暴走族と警察のいたちごっこなど、何かを捉えようとしても、結局はその「捉えようとすること」そのものが原因となって新たに逃げ道が作られたり、また裏をかかれることでいつまでも捉えられない、といった意味合いで使われ、類語としては「堂々巡り」や「無限ループ」といった言葉が使われることもあります。
それでは、「いたちごっこ」の語源、由来とは一体なんなのでしょうか。
あの動物の「イタチ」に、「いたちごっこ」のような習性があるのでしょうか。

いたちごっこという言葉は、動物のイタチではなく、実は江戸時代に流行った、文字通り「いたちごっこ」という遊びに由来します。
遊びのルールはシンプルで、二人一組になって「いたちごっこ」「ねずみごっこ」と言いながら相手の手の甲を順番につねり、両手がふさがったらいちばん下の手を上に持っていき、また相手の手の甲をつねるという、ひたすら手の甲をつねるゲームです。
ただ、この遊びは終わりがなく、終わりがない遊びというのが転じて、「いたちごっこ」という今の慣用句的な意味に変わっていったようです。
そもそも、なぜいたちごっこと呼ばれるかと言うと、手を素早く動かし、噛むようにつねるという動きから名付けられたようで、だから「ねずみごっこ」とも呼ぶのでしょう(イタチには、特に「いたちごっこ」のような習性もありません)。
ちなみに、「いたちごっこ」に英語訳などはあるのでしょうか。
もともと日本の遊びが語源のため、その状況をぴったり説明する英語訳はないものの、「悪循環」を意味する「vicious circle」や、永遠に終わらないという意味の「never ending」、また「Cat and Mouse」というイディオムもあり、これが一番意味合いとして近いかもしれません。
以上、「いたちごっこ」の語源、由来でした。